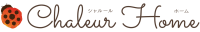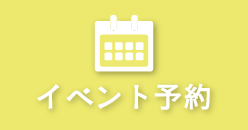窓は開けない!お風呂上りにすぐできる『カビ対策』
(2025.09.13加筆修正)
お風呂から上がったとき、何気なく窓を開けていませんか。
「湿気を逃がすために窓を開ける」
昔から当たり前に行われてきた習慣です。けれども現代の住宅では、その行為がかえって カビを招く要因になることをご存じでしょうか。
私たちがつくる家は、高気密・高断熱を基本とし、計画的な換気によって快適な空気環境を守る設計です。そこで本日は、建築的な視点から「なぜ窓を開けない方が良いのか」、そして「お風呂上りにすぐできるカビ対策」についてお話しします。
換気の本質を知ることから始める

カビの発生を防ぐには、湿気を効率よく外に出すことが第一歩です。ところが、換気はただ排気するだけでは不十分。新鮮な空気を同時に取り込む「給気」があってこそ、初めて循環が成立します。
換気方式には大きく分けて 第1種・第2種・第3種の3種類 があります。そのうち住宅で一般的に採用されているのは、第1種と第3種です。
-
第1種換気
排気・給気どちらも機械で制御する方式。外気はフィルターを通して取り込まれるため、空気の質を一定に保ちやすく、高気密住宅との相性が良いのが特徴です。窓やドアを閉めたままでも十分な換気が可能です。 -
第3種換気
排気は機械で行い、給気は自然に任せる方式。浴室ドアの下部にあるガラリや隙間から空気を取り込む仕組みで、戸建住宅で多く採用されています。ガラリがない場合はドアを少し開けて給気を補うとよいでしょう。
このように、どちらの方式でも「窓を開ける」必要はありません。むしろ窓を開けることで気流が乱れ、換気扇の性能が十分に発揮されなくなります。
窓を開けることで生じるリスク
お風呂から上がった直後に窓を開けると、一見湿気が逃げていくように感じます。ですが、実際には以下のような問題が起こりやすくなります。
・換気扇の排気効率が下がる
・外の湿気が浴室に逆流する
・温度差によって結露が発生する
つまり「入浴後すぐの換気は、窓を開けずに換気扇を活用する方が効果的」なのです。
もちろん、天気が良い日や入浴から時間が経って浴室がある程度乾いた状態であれば、窓を開けて外気を取り込むこと自体が悪いわけではありません。外気の風を感じたいときや、気候がカラッとしている季節などには有効な場面もあります。
大切なのは「窓を開けるタイミング」と「住宅の換気方式に合わせた使い方」。ここを知っておくことで、浴室を清潔に保ちながら住まい全体の空気環境を整えることができます。
お風呂上りに習慣化したいこと

シャルールホームがご提案する、シンプルかつ効果的なカビ対策をまとめました。
- 浴槽のお湯を抜く
浴室の湿気の大半は浴槽から生まれます。お湯を残していては換気扇も無力。入浴後は速やかに排水しましょう。 - 冷水で壁や床を流す
浴室が高温のままだと湿気がこもりやすくなります。冷水シャワーで壁や床をひと流しするだけで、温度と湿度を同時に下げられます。 - 換気扇を長時間運転
最低2〜3時間、できれば次の入浴まで。最近の換気扇は消費電力が小さいため、電気代の負担はごくわずかです。 - 浴室ドアは閉める
脱衣所や廊下に湿気を広げないために、入浴後は必ず閉めておきましょう。
この4つを意識するだけで、浴室のカビは目に見えて減ります。
換気設備を長持ちさせるために
せっかくの換気設備も、正しいメンテナンスがなければ性能を発揮できません。
- フィルター清掃
給気口のフィルターには外気のホコリや花粉がたまりやすいため、定期的な清掃が欠かせません。目詰まりすれば換気効率が落ち、湿気が抜けにくくなります。 - 換気扇内部のチェック
浴室換気扇には湿気やホコリがたまりやすく、放置すればモーターの負荷が増して故障の原因になります。半年に一度はカバーを外して清掃を。 - 24時間換気を止めない
電気代が気になってスイッチを切ってしまう方もいますが、24時間換気はその名の通り常時運転が基本。住まい全体の空気環境を保つためにも、常に稼働させてください。
こうしたメンテナンスの積み重ねが、住まいを健やかに保つことにつながります。
トイレの換気にも通じる考え方
じつはトイレも同じです。
窓を開けると一見気持ち良さそうに感じますが、換気扇の流れを乱す要因になります。窓は閉めたまま、換気扇を常時稼働させておく方が、においや湿気を効率的に排出できます。
福井の気候だからこそ必要な工夫

福井は日本海側特有の気候により、湿度の影響を強く受ける地域です。
冬は雪とともに湿気が住まいに入り込み、梅雨から夏にかけては高温多湿。年間を通して「湿気対策」が大きなテーマになります。
カビは「湿度70%以上・温度20〜30℃・栄養分あり」で発生します。つまり浴室は最も条件がそろいやすい場所。
だからこそ私たちは、 断熱・気密・換気を三位一体で考える設計を大切にしています。
お風呂上りに行うちょっとした習慣も、この設計思想と深くつながっています。設備の性能を十分に活かし、快適な空気環境を維持すること。それが福井の暮らしに寄り添う住まいづくりです。
まとめ
浴室のカビを防ぐ最大のポイントは「窓を開けないこと」。
現代の住宅は、昔の家とはまったく異なる環境性能を持っています。窓を開けるという旧来の習慣ではなく、換気システムを信頼して正しく運用することが何より大切です。
入浴後にお湯を抜き、冷水で室内を冷やし、換気扇をしっかり回す。たったそれだけで、浴室はぐっと清潔に保たれます。
シャルールホームは、地域の気候に合わせた 快適で健康的な暮らしを守る家づくり を追求してきました。お風呂上りの小さな習慣が、住まいを長持ちさせ、ご家族の健康を守る大切な一歩になります。
また、お電話やFAXでのお問い合わせも承っております。
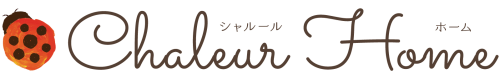
また、お電話やFAXでのお問い合わせも承っております。